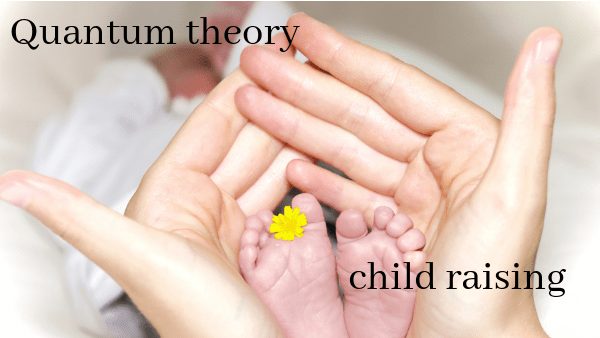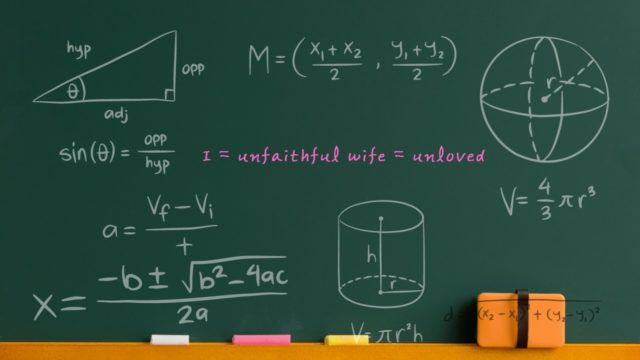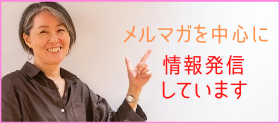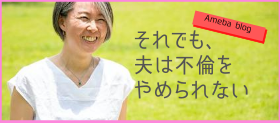子育てを楽しむための量子論活用法をお伝えするね!
子育てにイライラしてしまうのはなぜ?
子育てにイライラしてしまうのは、世のお母さんの悩みのタネ。
Twitterなどをみても、イライラしちゃうというツイートは多い。
子どもがうまく喋れない時や自分で身の回りのことをできない時期は、特にイライラしてしまいがち。
けれど、言葉が通じるようになり自分のことは自分でできる年齢になれば、イライラすることなどないとわたしは感じています。
むしろ、子どもが大きくなればなるほど、楽しくなっています。
が、周りを見るとイライラしてるお母さんは多い…。
そこで、子育てにイライラするのか、楽しいと感じるかの違いを量子論的に考察してみます。
生まれた時は「五体満足」ならばよかったはず
妊娠中や出産後、親は「とにかく五体満足ならそれだけでいい」と考えていたはず。
元氣に生まれてくれれば、何もいらないですよね。
だって、出産って命をかけてするものですもの。
成長するに従って、親は子どもが元氣なだけでいいとは思わなくなるんだよね。
あそこのお子さんは、もう歩いてる。
向こうのお子さんは、もうあんなに喋れてる。
そんな他者との比較や世間の目を通して子どもをみるようになるのです。
そのとき、我が子と他者との違いや世間の常識との違いを”個性”とみるか”劣っている”とか”遅れている”とみるかが将来大きな違いになります。
子どもへの期待は親の欲
子どもにイライラしている人の多くが、子どもへ「期待」しているように見えます。
では、「期待」とは何でしょう。調べてみると、
期待とは、何らかのことが実現するだろう、と望みつつ待つこと。
また、あてにして待つこと。
〈Wikipediaより〉
とあります。
つまりは、期待とは親の欲でしかないのです。
親が望みをもつことと子ども本人が望むことが同じであれば問題はないですが、違うのであれば親からの「期待」は子どもへ重荷にしかなりません。
子どもへの期待が大きければ大きいほど、裏切られたとき親は「イライラ」するはず。
まさに「期待はずれ」な状態ですね。
子どもには子どもの望みがあります。
それは親とは違うことがほとんど。
その擦り合わせができていないと、子育てにイライラしてしまうのです。
もう一つ、親自身が誰かの期待に応えることに疲れているということもあります。
「わたしだって頑張ってる」という人は、周りの人にも頑張ることを期待します。
親であるあなた自身が頑張り過ぎているのかもしれません。
子どもには「心配」より「信頼」を、「命令」より「お願い」を
”子どもには”と書きましたが、実際には他人を「心配」するなら「信頼」した方がお互いに心地よく過ごせます。
また、「命令」するよりも「お願い」する方が人間関係はスムーズになります。
「つい心配で…」とか「将来のために…」と、先回りして子どもを心配する親がいますが、それは子どもためにはなりません。
親は、子どもに大変なことが起きないようにするのが仕事ではなくて、大変なことが起こった時に対処する力を養い、何があっても安心できる場を提供するのが本来の仕事です。
心配してあれこれやってあげたり口を出すのではなく、子ども自身を信頼することが子育ての本質です。
家事を手伝わない、勉強をしない、などの悩みについても「命令」しても子どもは動きません。
大きくなればなるほど、動かないでしょう。
どうしても手伝って欲しいなら、「助かるのでやって欲しい」「助けてほしい」とお願いする姿勢で伝えましょう。
人間は、支配されることを本能的に避けるものです。
自我が出来上がってくる年齢なら、なおさら「〜〜しなさい」「〜〜やりなさい」では動かないでしょう。
子どもである前に、一人の人間として尊重する姿勢で子どもと接することが子育てのイライラを減らす秘訣です。
子育てを楽しむ量子論活用法
「子育てにイライラしないために」より、「子育てを楽しむには」という前提の意識の方が、親も子も断然楽しいはず!
わたしにとっての子育てって、大きくなればなるほどに楽しいものです。
そんな楽しい子育てを楽しむためにぜひ量子論を活用してください!
できないことよりできることに意識を向ける
この世界は、自分の意識が創ります。
エネルギーであり波である素粒子に”意識”が介在することで、物質になり現実を創るのです。

日本の教育は、100点を目指すものです。
できた95点よりできなかった5点をできるようにするもの。
そんな教育を受けてきたので、わたしたちもつい子どもの”できないところ”をできるようにしようとしてしまいがち。
小さな頃は、絵が上手いだけで褒められたのに大きくなったら「絵が上手いより勉強ができる」方がよしとされます。
けれど、量子論的に見るとできないことは放っておく方がよいのです。
できることに意識を向け、それを拡大させた方が天才性が発揮されやすいのです。
できないことをできるようにするために使うエネルギーをできることや好きなことに費やす方が本人も楽しいはずです。
本人が楽しく生きていれば、自ずと同じ周波数のものが引き寄せられます。
そうやって生きていくと、自然にその子どもの本質に見合った現実が創られていくのです。
子どもができることや楽しんでいることは何でしょうか?
それが将来役に立たないものでも、お金になることでなくても、その中に必ずその子の才能があります。
親として子どもが楽しんでいる姿は、それだけでしあわせなはず。
損得を抜きにして、子どものあるがままを見てみましょう。
「今もいい、もっとよくなる」という前提の意識をもつ
子どもに「勉強しなさい」とか「手伝いなさい」という時、あなたはどんな氣持ちでしょうか?
引き寄せの法則は「似たものが引き寄せられる」というもの。
自分が発した周波数に似たものが引き寄せられてきます。
子どもに小言を言っているとき、その周波数には”否定”が含まれているのでないかと思います。
その”否定”をせずに、注意するには今の子どものあるがままを認めることです。
「今の子どもはこう、もっとよくなるには…」という視点で話すことで子どもに伝わるものも変わります。
そのとき注意すべきは、自分の「期待」が混じっていないかということ。
自分が発した周波数と似たものが引き寄せられるのですから、否定の周波数を出せば同じように不快なものが返ってきます。
意識すべきは、子どもがどうか?ではなく、自分はどう感じているのか?なのです。
コントロールとジャッジを手放す
子どもを自分と無意識に同一視している親は多いです。
自分の価値観や想いと子どものそれも同じだと疑ってもいません。
そんな親がしがちなのが、子どもへのコントロールとジャッジです。
コントロールとジャッジは、子どもにもよい影響はないですが、一番悪影響を受けるのはしている親の方です。
コントロールしようとすることは、苦しみしか生みません。
なぜなら、他人をコントロールすることはできないからです。
できないことをしようとすればするほど、苦しくなります。
また先ほども言いましたが、人間は本能的に支配されることを嫌います。
「勉強しなさい」と言ってもしないなら、それは子どもの課題。
「片付けなさい」と言ってもしないなら、放っておくか親が自分の「快」のために動くか。
そこでイライラするのではなく、子どもの課題と自分の課題の境界線を引けているのかを確かめてみましょう。
ジャッジをするとき、人はネガティブな方に意識が向いています。
ポジティブな出来事をジャッジしようとはしないですものね。
子育てにイライラしているとき、わたしは正しいと思っていませんか?
「勉強するのが正しい」「家事を手伝うのは当たり前」などという感じです。
けれど、それは全て「自分の考えだけ」なのです。
人と人が関わる時には、必ず見解の違いが出てきます。
「これは、どう考えても、自分のほうが正しい」と、考えることがありますよね。
しかし、「どう考えても」というその「考え」は、自分のアタマで考えたことである以上、「どう考えても」自分の考えしか出てきません。
自分で考えれば、自分の考えが出てくるのは、当たり前の話です。
しかし、だからといって、その考えが正しいということにはなりません。
だって、考えている前提ー立場も体験も脳もーが違うからです。
〈反応しない練習 草薙龍瞬〉
コントロールもジャッジも、エネルギー的に重い波動のもの。
大切な子どもと向き合うときこそ、正しい自分でいるよりも素直で楽しいあるがままの自分でいたいですよね。
子育てのイライラは自分を成長させるチャンス
それでも、イライラするのなら!
それは、大きなチャンスです。
感情が動くということは、自分には違和感があるということ。
引き寄せがうまくいくのは、ワクワクに従うことと違和感を掘り下げることです。
自分の興味のあることを突き詰め、違和感のあるものを減らしていく。
その先に、その人の本来の在り方や本質があるのです。
感情が動くときこそ思い込みを外すチャンス
イライラしたり、怒りが湧いたり、悲しくなることは、自分の価値観と違うから。
それは、自分だけの思い込みが生み出しているものです。
以前、「長い行列ができていて、自分の買うものは一つだけだったので知り合いに頼んで一緒に買ってもらった」という話を聞いたときのこと。
人によって「ズルい!」「ルール違反!」と怒りを表す人と「頭いい!」「わたしもそうする!」という人に分かれたことがありました。
面白いですよね。
感情って、本当に人それぞれ違うものなのです。
子どもに関しても、服を裏返しに洗濯に出されるとイライラする!という親と何とも思わないけど…という親がいます。
どちらがいいか?という話だけではなく、その人の”当たり前”が感情の違いを生むのです。
自分をイライラさせる思い込みは緩めることでより楽に生きられるようになります。
持つべきこだわりもあるかもしれませんが、最強なのは「どちらでもいい」という中庸な姿勢。
それは投げやりになることではなく、「わたしはこう、あなたはこう」という他者との違いを受け入れることでもあります。
感情が動いたとき、その事柄や相手に意識を向けいていては、思い込みを見るけることはできません。
「全ては自分が創っている」のであれば、感情の動きの原因も自分の中にしかないのです。
自分のイライラが引き寄せるものを理解する
イライラが収まらない時、子どもに大きな声を出している親を見かけることがあります。
わたしは、とても残念に感じます。
そして、人として甘えがあるとも感じるのです。
イライラさせられてる、のではなく、イライラすることを自分が選択しているのです。
その意識がない上に、自分と同一化しているから子どもに大きな声を出せるのです。
(赤の他人にそんな大声は出さないはずですよね)
そんな自分のイライラを、自分の中で解決せずに態度や言葉で発するということは、自分からマイナスの周波数を発信しているということです。
つまりは、同じような周波数のものを自分が受け取ることになります。
イライライするな、と言っているのではないのです。
感情もエネルギーなので、しっかりと発散すべきですから。
イライラを出すなら、子どもにではなく後で一人になって大声を出すなり、書き出すなり、泣いてみるなりするという工夫をしてみましょう。
それは、相手のためというより自分のため、なのです。
親がゴキゲンなら子どももゴキゲン
「勉強しない」「手伝わない」「話を聞かない」「話をしない」など、子どもにもいろんな時期があります。
それは、子どもの課題です。
親がどうするものでもありません。
それよりも親が自分をゴキゲンにしておくことの方が、よっぽど大切なことです。
親がゴキゲンに過ごしていれば、波動が軽くなり周波数も上がります。
親の波動が軽く周波数が上がれば、周りも一緒に波動が軽く周波数が上がります。
周りをどうにかしようとしてもどうにもできませんが、自分だけゴキゲンになれば周りも勝手にゴキゲンになるのです。
量子論的な考えでいると、子育ては楽しいものでないはずがないのです。
自分の周波数を子どもが教えてくれるのですから、面白くないはずありません。
「まずは自分」、それは自分さえよければいいというものではなく、自分からしあわせを創るという覚悟なのです。
一人でも多くのお母さんがゴキゲンで過ごせると世界はどんどんよくなります。
あなたも今日から、楽しいお母さんで在りましょう!